このサイトでは建築学生向けに、主にCGパースのレタッチの仕方などを解説しています
なぜ表現手法を扱ったサイトを作っているのかについて書きました。
未経験でもプロになれる!専門学校をチェック!
- 代々木アニメーション学院(代アニ)
コスパよし!プロからしっかり学べるスクールはここ! - アミューズメントメディア総合学院
現場で活躍できるスキルを習得!
- 総合学園ヒューマンアカデミー
フレキシブルに学ぶ、実践重視のカリキュラム!
そもそも建築の表現手法がまとまったサイトが少ない
まず、そもそも建築のビジュアライゼーションを扱っているサイトが少ないことが挙げられます。
個人のブログレベルではちらほらと存在しているもののノウハウがまとまったサイトはあまり見かけません。
個人的な印象では、この分野に関して最も充実しているのは海外のサイト「Visualizing Architecture」ではないでしょうか。国内では建築パース.comさんなどが内容が充実していると思います。
ただ全般的に見るとやはり少ないと言えるでしょう。
特にモデリングの標準ソフトであるRhinocerosのリファレンスやレンダリングソフトのV-rayのリファレンスは乏しく、私も学生として設計課題に取り組む中でそのような課題を感じていました。
最短でプロのCGクリエイターに!
代々木アニメーション学院をチェック
無料で資料請求!
未経験でもプロになれる!専門学校をチェック!
CG(コンピュータグラフィックス)の世界は、映画、テレビ、ゲーム産業など多岐にわたり、プロフェッショナルを目指す方々にとって魅力的な分野です。
しかし、未経験からスタートする場合、どの専門学校を選ぶべきか迷ってしまうことも多いでしょう。
そこで、今回は未経験者でもプロを目指せる、おすすめのCG専門学校を3校紹介します。

学生だけではなく、社会人でも通いやすい学校をチョイス!
代々木アニメーション学院 | コストパフォーマンスに優れた学びの場

代々木アニメーション学院は、アニメーション業界で広く知られた専門校。
特に、3DCGコースは、6ヶ月間の学習期間で基本操作からCG作品制作までを学べます。
週1回の授業で、高校生から社会人まで幅広い年齢層が学んでおり、コストパフォーマンスの良さが魅力。
また、業界に精通した講師陣による指導は、基礎からプロレベルまでのスキルを身につけるのに最適です。
最短でプロのCGクリエイターに!
代々木アニメーション学院をチェック
無料で資料請求!
アミューズメントメディア総合学院【産学連携でプロデビューを実現!】

アミューズメントメディア総合学院(AMG)の「アニメ・ゲーム3DCG学科」は、未経験からプロへと成長するためのスキルを2年間で習得できる専門コースです。
指導にあたるのは、業界の第一線で活躍中の現役プロ講師陣。
バンダイナムコアミューズメントの開発経験者監修のカリキュラムを採用し、「売れるゲーム」のノウハウを学びながら3DCG技術を磨ける環境を提供します。
さらに、「AMG GAMES」産学連携プロジェクトにより、在学中から商用作品の開発に携わるチャンスも豊富。この実践経験が、プロデビューへの確かな道筋を築きます。
長く働けるプロになる!
アミューズメントメディア総合学院をチェック
無料で資料請求!
ヒューマンアカデミー|フルタイムで学び、プロを目指す!業界直結の全日制!

ヒューマンアカデミーの全日制「ゲームカレッジ CGデザイン専攻」は、未経験からでも本格的にゲーム業界を目指せる環境が整っています。
全国に校舎を展開しており、地元にいながらでも東京のゲーム企業とつながるチャンスがあるのが大きな魅力。
2D・3DCG、デッサンやムービー制作まで幅広く対応したカリキュラムで、ゲーム業界が求める即戦力を育成します。
さらに、就職直結の「ゲーム合宿」や企業とのコラボプロジェクトなど、プロに直結した実践の場が多数用意。
卒業生4,000名以上がゲーム業界へ就職している実績もあり、キャリア支援も万全です。
未経験からCGデザイナーになりたい方には、全日制のヒューマンアカデミーがおすすめです!
ヒューマンアカデミーをチェック
無料で資料請求!
資料請求・相談会は無料!気になったら今すぐ申込を!
なぜこうしたサイトが少ないのか
ではなぜこうしたサイトが少ないのでしょうか。これについては以下の2つの原因があると考えています。
- ニッチすぎてサイトとしてまとめる「うまみ」が薄い
- 建築分野とweb領域が近いようで遠い
順番に見ていきます。
ニッチすぎてサイトとしてまとめる「うまみ」が薄い
建築ビジュアライゼーションは、建築設計の中の一領域にすぎません。
さらにその建築設計も建設という大きなバリューチェーンの中ではそのパーツにすぎません。
しかもビジュアライゼーションの中をとっても使用ソフトなどの違いからニーズは分散しているため専門知識を扱うわりに、サイトとして知識が集約されていることでメリットを享受する人口は少ないと言えるでしょう。
使用するCADソフト一つをとっても10種類は少なくとも存在します。

CG技術が飛躍する中で、かえって手書き風パースなどの需要が高まっていることも「CGパース」の「ビジュアライゼーション」まとめの需要が薄いことの立証になりそうです。
(実際、検索上位に入っている建築レタッチ動画でもYoutubeでの再生回数は数千〜数万回程度とあまり多くはないのが実情です。)

かなりニッチなんだよね・・・
建築分野とweb領域が近いようで遠い
建築分野では最近ではCADの普及によってITの存在が昔に比べてかなり身近になりました。
が、建築の設計分野は基本的にwebマーケティングによって受注することはないのでwebの専門知識が業界全体としてそれほど必要とされていないことがボトルネックになっていると個人的には考えています。
例えばサイトに関して、httpsではじまるSSL対応が標準ですが、建築関連のキーワードで検索した際に上位ヒットするサイトはURLを見るだけでもあまりそうした対策は行われていないことが分かります。
webというもの自体が今後どうなっていくかわからないし、こうしたSEO対策といったものも10年後には不要になっている気がしますが、これから2020年にかけて瞬間的に建築業界が好況を迎えることを考慮に入れると建築学生のニーズが数年はまだ存在するだろうという予測からサイトを続けています。

結構いろいろ考えてサイトをやっています
なぜビジュアライゼーションを扱うのか
ここまで読んだ方は、
「じゃあなんでこのサイトは建築の表現手法をテーマにしてるの?」
と思われたかもしれません。
設計における本質が課題と、そのソリューションであるならばプレゼンテーションの質や表現の巧拙は重要でないことになるでしょう。
全くその通りです。
ではなぜ表現手法についてこのサイトで扱っているのか。
それは、本来重要であるべき課題設定やソリューションの提示に使うべき時間が、手段にすぎない表現への「こだわり」の時間に費やされている懸念があるためです。
表現を実現するために、例えば
「こういう感じの図面に仕上げるためにはどうやってレタッチしたらいいんだろう?」
と思い、パソコンで調べる時間は言葉を選ばずに言えばアウトプットに直結せず、時間の無駄です。
英語のサイトを頑張って調べてレタッチの技術を学ぼうとする時間も同様です。
そしてこれは「できる学生」と「できない学生」の格差をうむ遠因になります。
なぜなら表現が器用にできる人はそうした無駄な時間が少なくて済むのに対し、不器用で表現手法のインプットが乏しい人ほどそうした時間が多くなりがちだからです。
また、こうした調べ物の時間や表現手法のインプットに投じる時間が多いことは、建築学科がブラックと言われるように、学生の作業時間を増やすことにもつながると思っています。
このサイトが解決したいのはまさにそういう課題で、毎回表現の仕方の調べものに時間がかかってしまう学生が、「うまく表現できない」と悩む時間によって本来使うべき思考の時間を奪われないようにしたい、そのために表現の巧拙によって生まれる格差を無くしたいという理念に基づいて運営をしています。
ここまで偉そうに書いてきましたが、これは建築学生として過ごしてきた筆者の主観に基づく、ごく断片的な考察にすぎません。
今はまだ記事数も乏しく、コンテンツもそうしたニーズに応えられるレベルには全然なっていませんが、「表現に関してはこのサイトを覗けばだいたいなんとかなる」の状態を目指して頑張ろうと思います。

みんなに使ってもらえるサイトになったら嬉しいな!

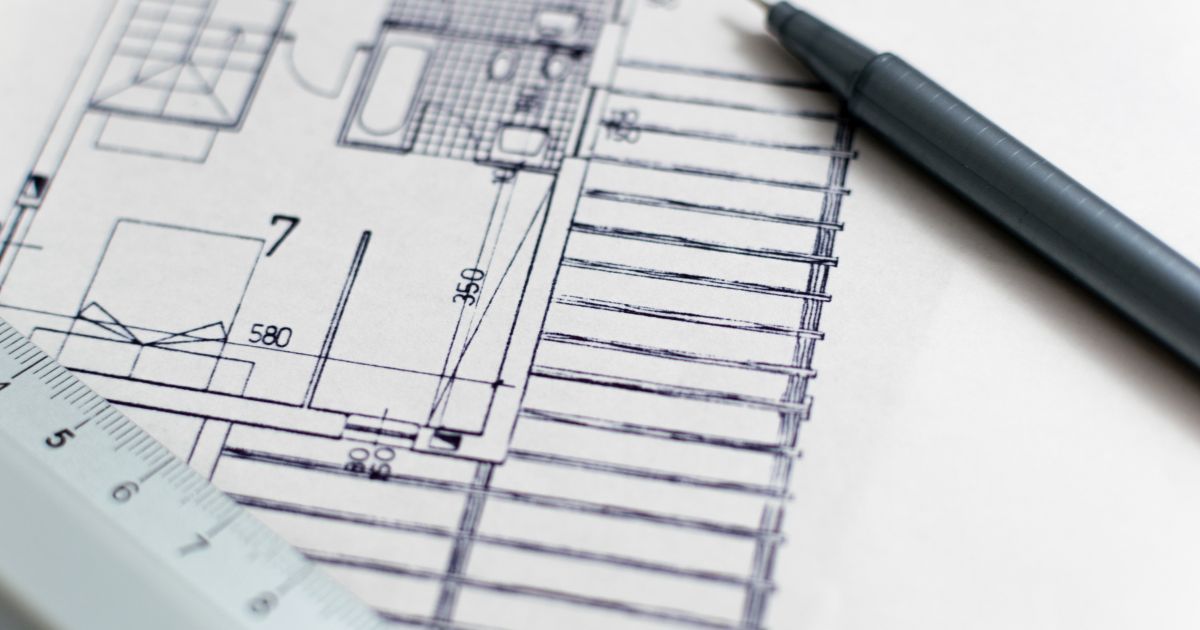

コメント